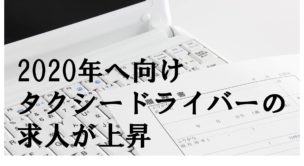
タクシードライバーの求人募集数が急上昇!?
景気の変動は常につきものですが、タクシー業界はというとカーシェアリング・自動運転技術などの登場により利用者が減少していると思いきや、実働1日1車当たりの運送収入(日車営収)は17年前とほぼ同じなのです。
2002年新規参入や増車が自由化され業界の急成長をみせたが、2008年リーマンショック後にタクシー業界のバブル崩壊、その後長らく不況が続いたものの、2017年ごろから2019年には順調に復活の兆しを見せています。
日本交通では「相乗りタクシー」アプリを試験導入したり、他業種であるIT業界から(タクシー企業側のいい悪いは別として)「タクシー配車アプリ」、2020年東京オリンピックに向けたJPNタクシー車両導入など、新たなサービスを提供・導入することによって、お客様との接点が増え、進化を遂げているのが現状です。
ただ、景気が良くなったとはいえ、給料にすべてが反映されるわけではありません。これはサービス業という職業柄、1人(台)で稼げる金額には限りがあるからなのです。
例えば、1名のお客様でも4名を乗車させても収入は変わりませんし、お客様を乗せている時に他のお客様は乗せられないため、生産性(=収入)を爆発的にアップさせることは難しいのです。
タクシードライバーの平均年収は他産業労働者に比べて低いことは確かです。拘束時間や労働量に対して少々割に合わない印象を持たれがちですが、それ以上の魅力があるこの業界。
というのも、タクシーという交通手段は(重要度のレベルは別として)公共交通機関ほどのルールが定められ、価格競争や車両過剰の事態を防ぐことで、タクシー業界で働く人の労働環境が不安定にならないよう、公平性を保っている業界なのです。
とはいえ、サービス業全体に言えることですが、人手不足はタクシー業界にも影響を与えており、企業側は常に求人をしている状況であるといえます。
ドライバーの高齢化や早朝から深夜まで続く不規則な勤務は負担になるなど、タクシードライバーをするにあたって、体質的に適応しているかしていないの問題もあります。
それとは別の理由として、企業は景気が良くなっているからこそ、多くのお客さまを乗せられるように、営業できるタクシーの台数を増やしたいのです。
ただし、タクシーを運転するドライバーを増やしてからでないとタクシーは営業できませんよね。業界の景気がよくなると、人材不足になる仕組みになっているのです。
現在、事業拡大のための求人が多く出ており、就職希望者は企業の求人数を下回っているのが現状。
ドライバー側は企業を選べる立場にあり、待遇や福利厚生を比較し、最も良い条件の就職先を見つけることができるのです。
今後も状況は変わらないことが想定され、首都圏での自家用車を持たない人はさらに増加し、地方では高齢化による移動手段の需要も上がっていくことでしょう。さらにITとの関係を良好に築くことさえできれば、より利用者にとってタクシーは便利で身近なものになっていくことは間違いありません。
2020に向けて求人率は2倍に。企業を選ぶ立場に
2020年に東京オリンピックという大きなイベントを機に海外から訪れる観光客数は東京都の予想でのべ1500万人。約42会場の開催地のうち、約21会場が東京都内に設けられています。
東京都の昼間人口が約1500万人、オリンピック開催期間中の海外からの観光客1500万人が東京一堂に介する場合、なんと東京都の日中人口は3000万人にものぼることが想定されるのです。
多くの交通機関が利用される中で、タクシーというのは重要な交通手段のひとつとなり、真夏の炎天下では国内外の観光客の利用者が続出することでしょう。
東京都近郊企業では、高齢者や車椅子を利用される方、外国人旅行者などが快適に利用できるユニバーサルデザインを採用したJPN TAXI(ジャパンタクシー)といわれる新型車両を開発し、1万台の導入を目指しています。
タクシーにはこれまでなかった、車椅子に乗ったまま乗車できる設計になっており、乗り降りもドライバーが用意するスロープで対応可能となりました。ユニバーサルドライバー研修という制度もあり、高齢者やお身体の不自由な利用者とのコミュニケーション、車いすの取扱いや乗降時の介助方法などについて研修制度がとられています。
車内にはほかにも多くの工夫が施されており、国内外のすべてのお客様にとってより快適な時間が過ごせる空間にもなっています。
英語接客への資格取得サポートも完備
タクシードライバーへの対応方法研修のほか、タブレットでの接客応対や、配車アプリの多言語対応などで、あらゆる手段でタクシー業界のサービスもグローバル化を進めています。
英語で観光案内・接客・通訳を行う認定制度
TSTiE(タスティー)ドライバー認定制度といわれる、都内のタクシードライバーを対象に、TOIC600点以上(または同等の)英語力と、東京都が主催する最大56時間の研修を経て資格を取得することで「東京都地域通訳案内士」として通訳案内や通訳ガイドをおこなうことができます。
研修では、通訳案内士法・旅行業法に関する知識に加えて、AED の取り扱いや救急(救命) 手当の知識・技術も学びます。
東京都は2020年までにこのドライバー認定士を300人まで増やす予定です。
(東京都産業労働局、【募集要項】東京都地域通訳案内士認定研修、2019.2.17)
配車アプリの多言語対応で、外国語対応も必要なし
日本最大級の配車アプリ「japan taxi」では、日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)に対応し、訪日旅行客の約80%の言語をカバーできるようになっているので、地図上に表示された目的地を見つけられるのです。
さらに、現在どこを走っているのかをアプリ上で確認しながら目的地までの道を確認しながら乗車できるため、着いたら違う場所だったというクレームは圧倒的に少なくなります。
さらに降車時の決済アプリ「JapanTaxi Wallet」では中国で最も利用者が多いといわれる決済方法AirPayにも対応し、クレジットカードから支払いもできるシステムも完備。言語によるコミュニケーションが取れない場合もQRコードを読み取るだけなのでストレスなく、スムーズに利用できるのです。
複雑といわれている東京の交通手段ではこのアプリを駆使している旅行客もすでに多く、今後も活用されていくこととなるでしょう。